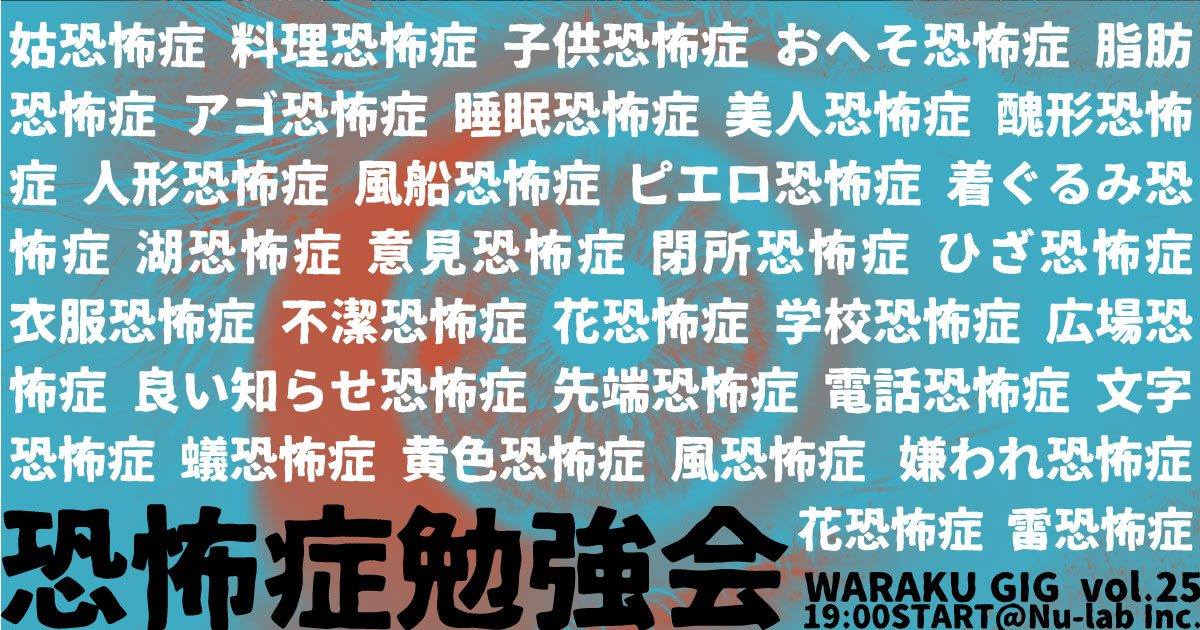日本全国でイノシシやシカによる農作物被害や、街に出現するなどのトラブルが深刻化している昨今。獣肉の一次処理・精肉および加工・販売を担い、ジビエ産業を次世代へと受け継ぐべく奮闘しているのが、若干24歳、自らを捌師(はちし。「捌」は肉などを「さばく」の意)と名乗る糸島ジビエ研究所代表の西村直人さんだ。

イノシシをさばいてみない?
「中高ともに豚を育てたり畑作業をしたりと、生活の中で自然と触れ合うような教育方針の学校に通っていたので、結果的にこの道を選んだことも特段新しい分野に挑戦しているという感覚はなかったんです」
契機となったのは、西村さんが九州大学在学中に受講した「食」に関する生物系ゼミだった。具体的に何を研究するかは自由だったことから、“そもそも食べるってどういうこと?”をテーマに掲げた。
「人間以外の生物と同じように自然を食べ物として捉えた時、その捉える前と後でどう見え方が変わるのかを経験しようという意図です。具体的には、糸島市を一日歩いて採れた食材だけを使ってご飯を作る、などといったような活動をしていました。そんな活動をしているうちに知り合った方から『イノシシをさばいてみない?』と、声をかけてもらって。それが四足獣との出会いでした」
中高生のころ、授業の中で豚を育てたことがあったという西村さん。しかし、育てた豚を出荷した後は肉に加工されて戻ってくる仕組みになっており、「生き物を食用に処理する」という一番重要なところを経験できていないという思いがあったため、二つ返事で誘いに応じた。

就職するよりも自分が正しいと思うことを
「声をかけてくださった方が、のちにぼくが通っていた九州大学の学内で行われていたイノシシの捕獲を担当されるようになったんです。それから捕獲されたイノシシを一緒にさばいたり加工したりするようになりました。せっかく学内にそんな環境が備わっているのならば勉強の機会にしようと、大学2年の時に狩猟研究会を立ち上げました」
大学入学時は将来教育関係に進みたいと考えていた西村さんだったが、狩猟研究会の立ち上げなどを経験したことで将来に対する考え方が変化し、就職活動は食品メーカーを中心に行った。大学3年生の終わりごろには数社から内定をもらったというが、一方で「本当にこれでいいのか」という葛藤に悩まされた。
「イノシシやシカの正確な個体数把握や適切な個体数の算出が難しいのが現実です。にも関わらず近年はひたすら駆除を進める風潮が強い。また、“害獣対策”の一貫としてある種のブームになっているジビエ(狩猟によって食材として捕獲された野生の鳥獣)が、『捨てるものを活用する』という考え方に立脚している点にも危機感を感じていました。
そんな悩みを先輩などにも話し、アドバイスをもらう中、結局就職するよりも自分が正しいと思うことを自分自身でやってみた方がいいんじゃないかと考え、大学4年生の11月に起業しました」
捕獲を通じ、あるべき生態環を目指す
「イノシシやシカはこれまでも『激増』と『激減』を繰り返してきました。現在は、街にイノシシやシカが降りてくることをニュースなどもよく見かけるように、激増の時期なんです。だから捕獲して数を管理しています。
街で暮らしているとどうしても『自然vs人間』という考え方になってしまいがちです。しかし、本来は人間も動物もひとつの大きな生態環の構成者として考えないといけない。
魚などのほかの天然資源同様、おいしい食料・良い素材だから漁獲・捕獲を行い、取りすぎにならないよう資源管理の考え方をしっかり実践することこそ、捕獲のあるべき姿です。そういう仕組みが機能していれば、野生動物は適正な数に保たれて被害もなくなり、“害獣”という言葉もなくなると思っています。わたしが実現したいのはそうした仕組みを持続していくためのビジネスモデルの構築です」
そのためにまず必要なのは、ジビエを「捨てるものの利活用」という発想ではなく、立派な「食材」として正当に評価する消費者感覚の形成だと西村さんは力説する。

「ジビエは供給が不安定、かつ少量で、精肉コストも大きい。けれど適切に処置したものは実際和牛並の食材として十分勝負できるんです。そのことを消費者に知ってもらえれば、品質に伴うまっとうな相場を築くことができるはずだと考えています」
西村さんが日頃から感じているのは、一般的な認識としてジビエ=臭い・かたいという誤った認識を持っている方がとても多いということ。そうした認識が広まっている以上、ジビエが日常の中に溶け込むのは難しい。まずはそのネガティブなイメージをゼロに戻す作業が大切だと考え、イベントなどを積極的に開催している。
「わたしたち捌師・解体業従事者は、和牛並の評価を当たり前に受けられる高品質の肉、ならびに皮他の素材を提供していくのが仕事です。現状の市場環境において、一般の人は『おいしくない』と思っている人が多いので、イベントなどを通じて、買いやすいく手に取ってもらいやすいような廉価商品で、ネガティブイメージを払拭してもらう必要があります。
ただあくまで、ネガティブイメージの払拭が目的ではなく、その先の『やっぱりシカ肉うまいね』『このイノシシは高値出すだけあるね』ってところをまで持っていくということを目標にしています」

テクノロジー連携が取り組みを加速する
最終的には、山や海など自然が豊かな地域で、カフェとも宿ともレストランともとれないような空間を作ることを目標に掲げているという西村さん。
「そこに『ジビエを食べに行く』のではなく『いい時間を過ごしに行く』という、日常の延長のような感覚で人が集まってくれるような空間ですね。ジビエの第一のゴールが、自然の中で人間が生きているという意識が根付くことだと思っているので、そういう意識を持つきっかけにもなる空間をいつかつくりたいと考えています」
また、糸島ジビエ研究所では現在、セキュリティーサービス会社の綜合警備保障株式会社(ALSOK)が開発している罠の監視装置を取り入れており、西村さんはその設置指導を行っている。
「箱罠装置とメールが連動しており、罠が作動すると監視装置が自動で起動。管理者にメールで通知される仕組みです。この装置の導入により、見回りに掛かる労力の低減や錯誤捕獲の早期発見、オリやわなの稼働率向上、早期の止め刺しによる食肉としての価値向上が期待されます」
イノシシなどの解体や加工品の製造販売、イベントなど、あらゆる方面から食肉の価値の普及や生態系管理に取り組む西村さん。そこへさらにテクノロジーを連携させることで、彼が思い描く理想的な生態環は、より一層現実に近づくだろう。今後の取り組みに目が離せない。

その他の特集記事
・【次世代のための食の循環①】生ゴミをオーガニック肥料に! manucoffeeと土壌研究の専門家。異色タッグが取り組むアップサイクル